2019/07/05
季節の変わり目に誰しもが体の変化や不調に悩まされた事があると思います。
気持ちの問題かな?
自律神経のせいかな?
など原因を探せば様々あると思います。
思い返してみると、子供の頃そんな記憶ありますか?
春だから体調悪いな
夏だから外で遊びたくないな
秋はなぜか夏のせいか胃がもたれるな
冬は冷え性が。。。。
という記憶はあまりないのではないかと思います。
季節も温暖化といえ、ここ数十年、多少変化はありますが、真夏の異常気象以外はさほど人体に影響を与えるレベルはなかったと思います。また、現代はエアコンの普及により、夜などもエアコン使用でそこまでは『暑さ』にたいしては対策がとれてると考えます(昔はエアコンは普及してないため)
変わったのは、季節よりも人間のエネルギー(東洋医学でいう『気』)や自律神経だと考えます。
ここでは東洋医学である『気』がまずは季節で変化する事を説明していこうと思います。
気とはエネルギーです。
このエネルギーも『外邪』(環境)『内邪』(ストレス)にやられるとどんどん奪われていきます。奪われると、免疫力低下など体の抵抗力にかかわってきます。
先ずは外邪について説明します。
外邪とは6つあります。
1つ目は風邪
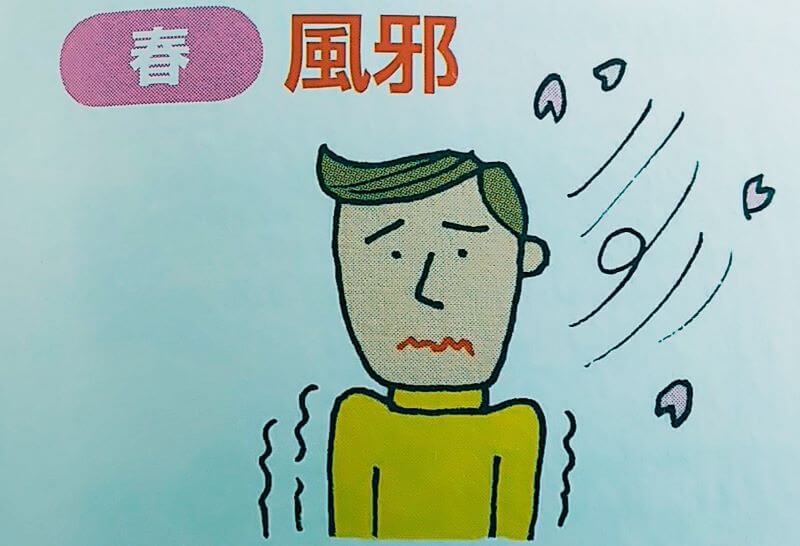
主に春に起こりやすく、春一番のように突然起こってきます。
五臓では肝に不調を招きやすいです。
例)春のうつ症状 イライラ
2つ目は湿邪

ジメジメした梅雨のように体の重だるさを引き起こし、冷えや神経痛(鈍痛)に関係します。
また五臓では『脾』『肺』『腎』に影響します。
脾→胃腸障害→食中毒
肺→免疫力低下→風邪
腎→代謝→むくみ・おもだるさ 腰痛

3つめに厚邪
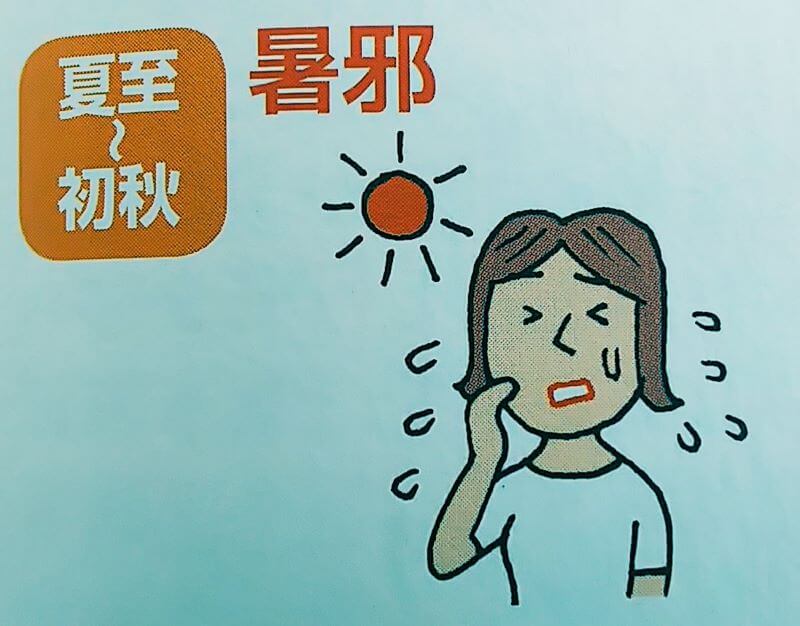
蒸し暑い日本の真夏のように、熱と湿が入り混じった外邪。
顔が赤くなったり汗が出すぎたりします。

熱がこもりイライラや動悸、また熱中症などがあげられます。
4つめは燥邪
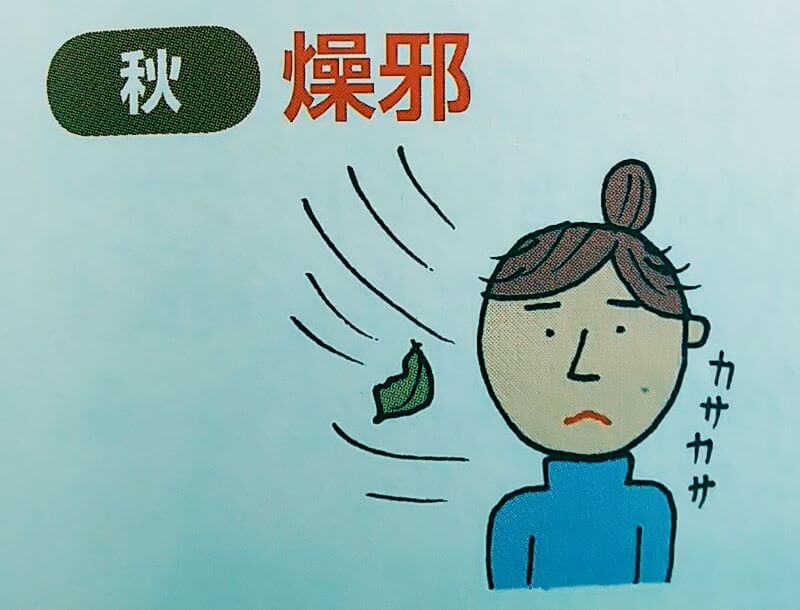
秋に起こりやすく、パサパサした乾いた枯葉のように乾燥した外邪
肺に影響し、呼吸器や表皮のトラブルを招きやすい。
例)肌の潤い 風邪(ぜんそくなど)

5つめは寒邪
冬に発生しやすく降りしきる雪が体の熱を奪うように、体内を冷やして、『気』『血』『津液』の巡りに影響を与え、『腎』にも関係します。
例)冷え性

6つめは熱邪
先ほど紹介した5つの邪がさらに変化すると『熱邪』となります。
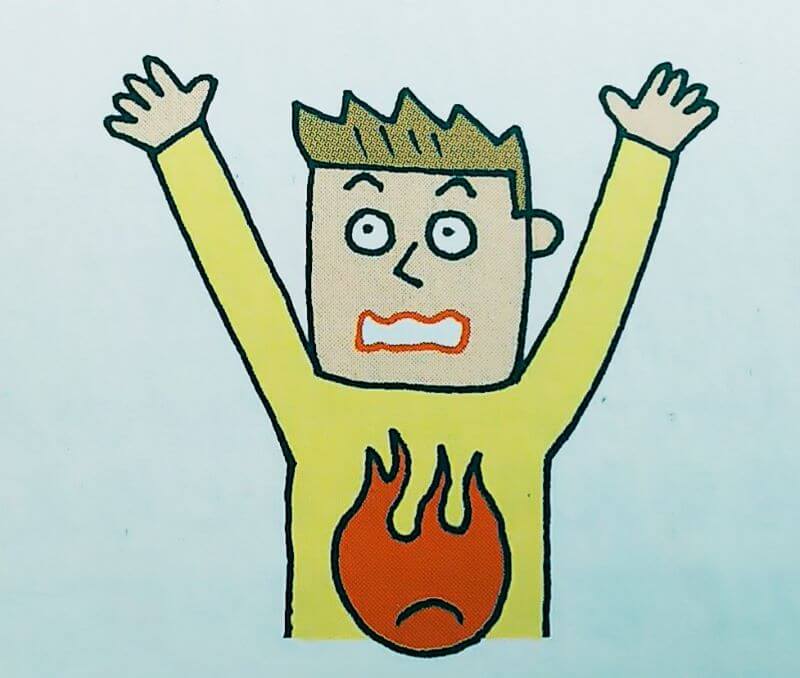
体が熱を持ち、発熱と炎症を繰り返します。
いわゆるこれが発病です。
東洋医学では先ほど紹介した5つの邪、つまり『未病』の段階で体の調子を整え、未然に防ぐつまり、予防する事に力を入れています。